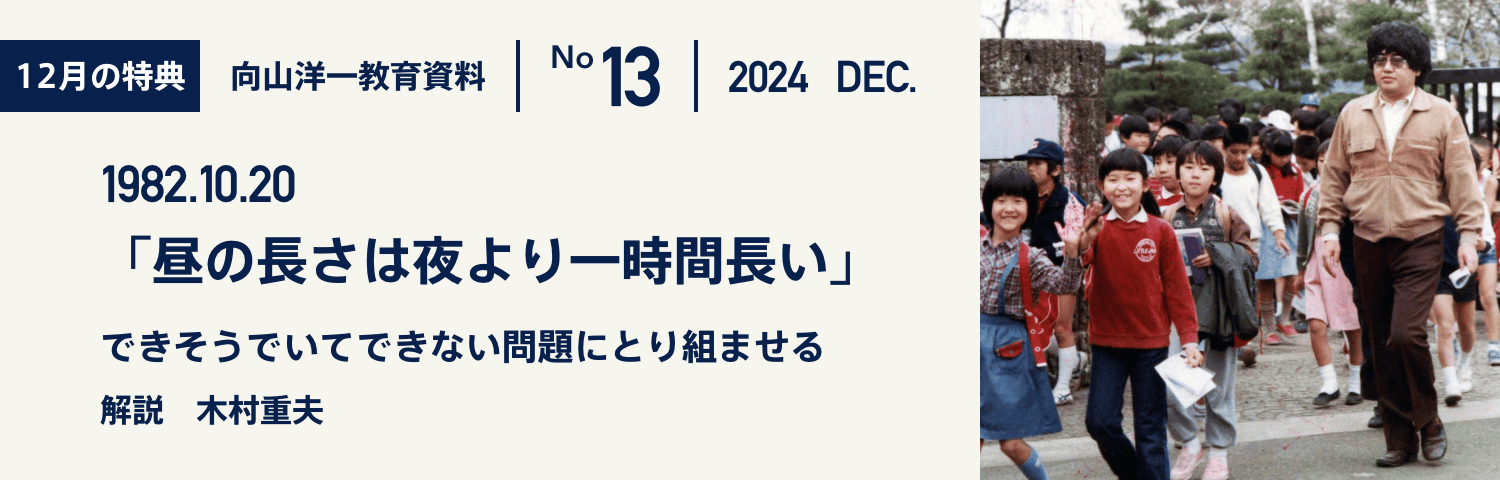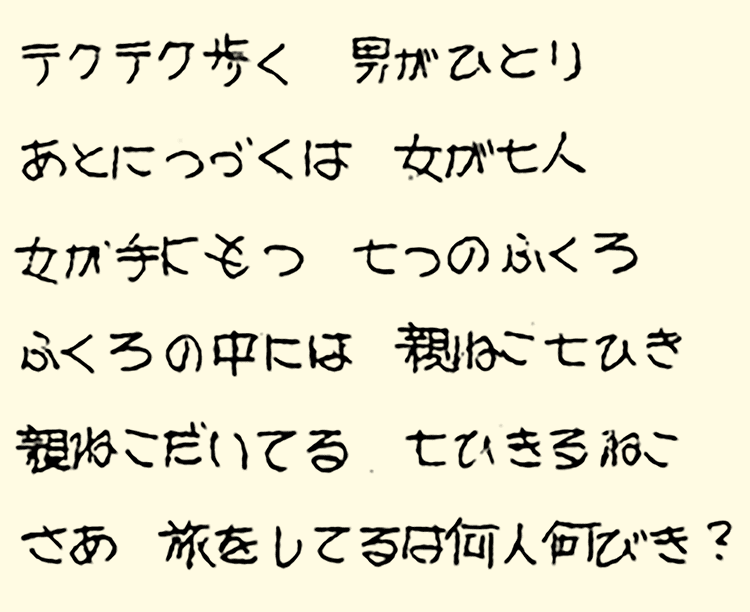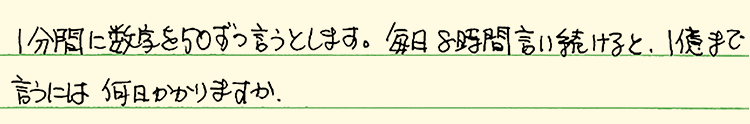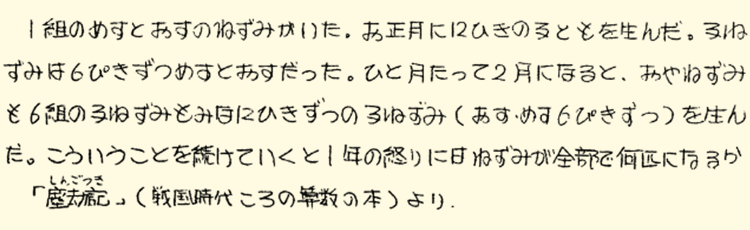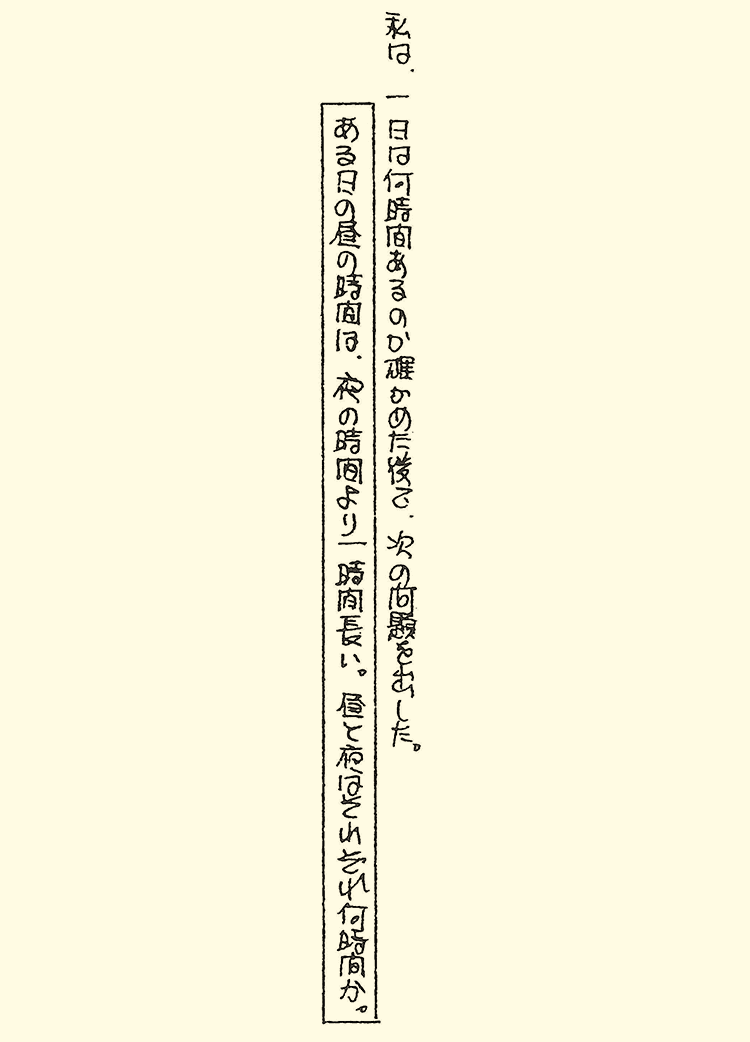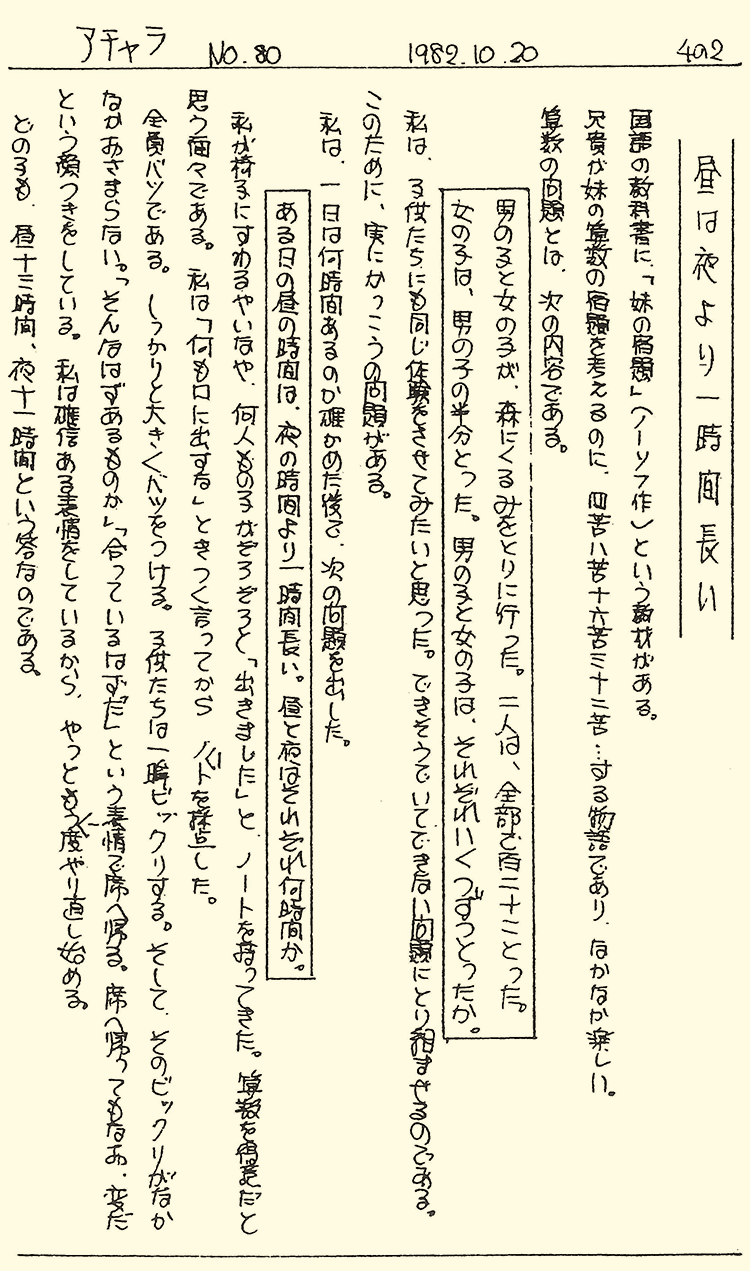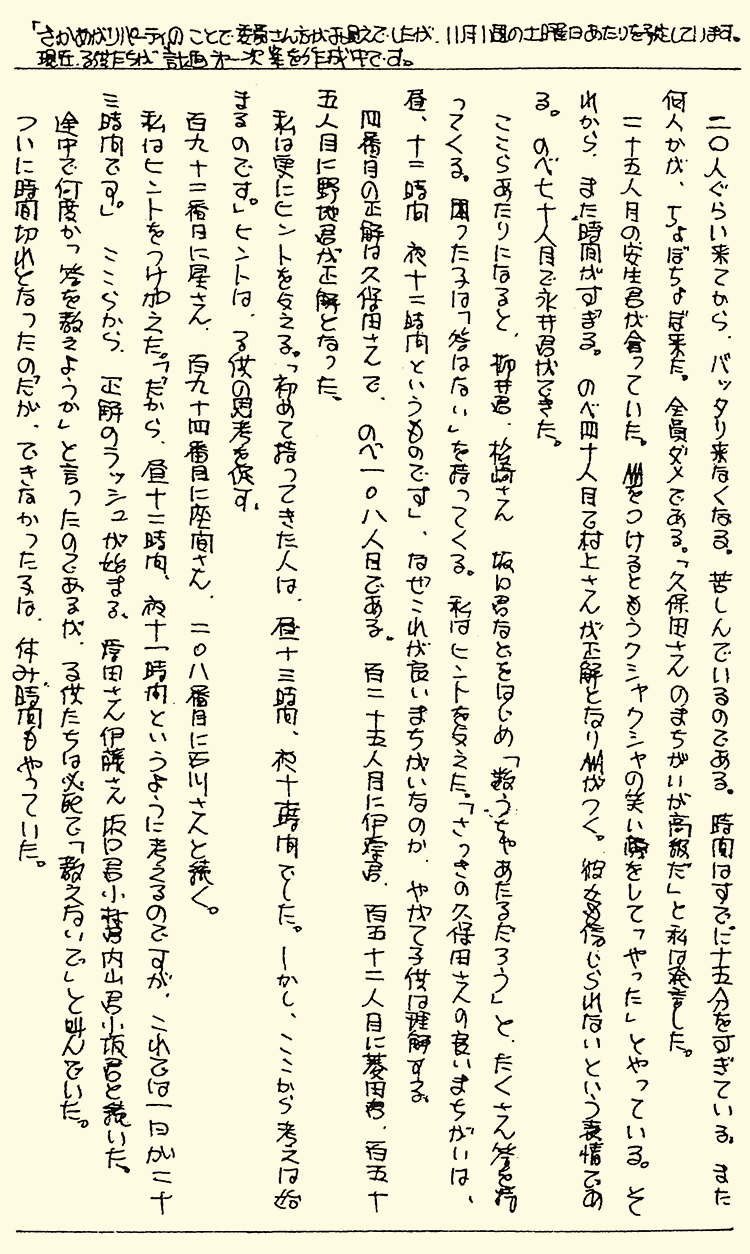|
つまり、向山は問題をいう前に
|
|
一日は何時間ありますか?
|
|
と聞き、
|
そうですね。
一日は24時間ですね。
|
と確かめたうえで、問題文を板書したのです。
なぜ、向山は、問題を提示する前に一日の時間を確認したのでしょうか。
問題を提示した後に一日の時間を確認しても、あまり変わらないのでは?
おそらく
「そのほうがいい」
と直感したのでしょう。
もし、先に問題を提示したらどうなるでしょうか。
問題を読むスピードが子どもによって違います。
理解するスピードも違います。
「先生、一日って24時間ですよね」
などという質問をする子もいるかも知れません。
すこし混乱しそうです。
どちらがいいかは、100点対0点ではありません。
でも、向山という超一流が現場で直感的にやることです。
それには、理論より先に何かあるかもしれない・・・
そう考えて、私は追試してきました。
そのほうがうまくいく感覚があったからです。
実践は常に理論より広い。
超一流が無意識にとっている行動。
それがやがて理論化されていく。
|
|
理屈じゃない、実際そのほうがいい感じがするんだ。
|
|
みたいな感覚です。
|
 |
| 3 子どもがノートを持ってきたら |
手順1:一日は何時間あるのか確かめる
手順2:問題を出す
|
さて、手順3は?
『アチャラ』を持っている人は、まず見ないで推定していただきたいところです。
・
・
・
手順3はこれです。
|
|
手順3:椅子に腰かける
|
何も言いません。
黙って教卓の椅子などに腰かけます。
子どもたちが慣れていないなら
「できたらノートをもっていらっしゃい」
程度は言ってもかまいません。
子どもたちが、
「できました」
と言って、ぞろぞろとノートをもってきます。
この後が「手順4」です。
ノート持ってきた子たちに対してどう対応しますか?
いかがでしょうか。
多くの方が
「黙って◯か×をつけてあげる」
のように考えたのでは?
私もそう考えました。
でも、違うのです。
それも『アチャラ』に書いてあります。
|
|
私が椅子にすわるやいなや、何人もの子がぞろぞろと「出きました」と、ノートを持ってきた。算数を得意だと思う面々である。
|
この後です。
ここでのポイントは、
|
|
算数を得意だと思う面々である。
|
という表現です。
もっと絞ると
|
|
面々
|
という表現です。
この後、その「面々」に向山はこう言いました。
・
・
・
|
|
手順4:何も口に出すな
|
|
正確には
|
|
私は「何も口に出すな」ときつく言ってから、ノートを採点した。
|
と書いてあります。
ノートを我先にと持ってきたのは一人ではありません。
数名がぞろぞろとやってきたのです。
最初に来た子だけに言うのではありません。
「面々」に、つまり持ってきた全員に言うのです。
「何も口に出すな」
おそらくは教室全体に聞こえる程度の声でしょう。
その上で採点したのです。
どうして、「口に出してはいけない」のでしょう。
×をつけられた子が、
「えーっ、なんでーーー!!」
とか、言い始めるかも?
それはそれで盛り上がって楽しいような気もします。
でも、ここではあえて、声を出させない。
そのほうが、全体が熱中する。
向山はそう直感したのでしょう。
これも、理屈はつけられそうな気がします。
でも、理屈以上の何かがあるような感じもします。
「口に出してもいい」
という設定でもいいかも知れません。
それなりに熱中するかも知れない。
それは、わかりません。
みなさんがいろいろとやってみればいいです。
私の場合は、
「まずは一流をトレースする」
ことを選択したということです。
あ、ちなみに
「何も口に出すな」
という言い方が、令和の時代ではちょっとキツい?
だったら、
「絶対に声を出しませんよ」
みたく言ってもOKだと思います。
|
 |
| 4 しっかりと大きくバツをつける |
|
さて、その次の手順5はいいですね。
|
|
手順5:しっかりと大きくバツをつける
|
「しっかりと大きく」がポイントです。
子どもたちはびっくりします。
声を出しそうになります。
でも「口に出すな」とさっき言われたばかりです。
必死にガマンします。
「そんなはずあるものか」
「合っているはずだ」
という表情で、ゆっくりと席へ帰っていきます。
ノートと先生の顔を見ながらです。
席についてもまだ
「変だ」
「おかしい」
という顔つきをしています。
ここで次の手順です。
教師はどういう態度をとりますか?
はい。
・
・
・
|
|
手順6:確信ある表情をする
|
教師は自信たっぷりの表情です。
確信をもってバツをつけるのです。
|
 |
| 5 向山学級での子どもたちの反応 |
ここから先は、向山学級とあなたの学級で差が出ます。
子どもたちの実態が違うからです。
向山のとおりに完全に追試することはできません。
「現場での応用問題」です。
でも、だいたいはトレースできます。
『アチャラ』に記録が残っているからです。
参考のため、向山学級での子どもたちの様子をシミュレートしておきましょう。
|
1)最初に持ってきた子たちは全員バツ
(「昼13時間、夜11時間」と書いている)
2)20人くらい全員バツ
3)バッタリ来なくなる。苦しんでいる。
(ここまでで15分をすぎる)
4)何人かがちょぼちょぼ来る。全員バツ。
|
ここで「久保田さん」だけが違う間違い方をします。
向山は当然、それをその場で見取ります。
そして「ちょっと介入」するのです。
|
5)【介入1】
久保田さんのまちがいが高級だ
|
ところが
「久保田さんはどんなまちがい方なのか」
は言いません。
子どもたちは考えます。
「久保田さんのまちがいは高級?」
「まちがい方に種類があるのか?」
|
いろいろなまちがい方がある
高級なまちがい方もある
|
そう思った子どもたちは、さらに熱中します。
たとえバツでも、それが高級かも知れないからです。
|
|
6)25人目の安生君が正解。AAAをつける。
|
安生君はクシャクシャの笑い顔。
「やった」となります。
|
7)また時間がすぎる。
8)のべ40人目。村上さんが正解。AAAをつける。
9)のべ70人目。永井君が正解。
10)柳井君、松崎さん、坂口君など
「数うちゃあたるだろう」の子がたくさん答を書く。
11)困った子が「答えはない」と書いてくる。
|
|
ここで、向山は2回目の介入をします。
|
12)【介入2】
さっきの久保田さんの良いまちがいは、
昼12時間、夜12時間というものです
|
ここで「久保田さんの良いまちがい」を発表するのです。
ところが、
「それがなぜ良いまちがいなのか」
は一切説明しません。
|
|
「事実と教師の評定」だけを淡々と伝える
|
のです。
久保田さんのまちがいはなぜ良いのでしょうか。
そうですね。
「昼が夜より一時間長い」
「一日は24時間」
この2つの条件と
「格闘している」
からです。
他の子たちの答は
「24時間を2つに分ける」
ということだけで安易に結論しています。
13時間と11時間では2時間違ってしまうなあ・・・
じゃあ、12時間と11時間なら?
だめだ、23時間になってしまう。
・・・12時間と12時間かな?
このように格闘したのが久保田さんの答えです。
2つの条件を考えて悩んでいるからこそ、
「良いまちがい」
になるのです。
|
13)なぜこれが良いまちがいなのか、
やがて子供は理解する
|
と、向山は書いています。
説明しなくても、自分たちで突破してくるのです。
|
14)のべ108人目。四番目の正解は久保田さん
15)125人目。伊奈君が正解。
16)152人目。菱田君が正解。
17)155人目。野地君が正解。
|
ここで向山は3回目の介入をします。
おそらく、授業の終了時間を気にしたのでしょう。
|
18)【介入3】
初めて持ってきた人は、
昼13時間、夜11時間でした。
しかし、ここから考えは始まるのです。
|
|
このヒントが子どもの思考を促します。
|
19)192人目。星さんが正解。
20)194人目。座間さんが正解。
21)208人目。石川さんが正解。
|
|
向山の4回目の介入
|
22)【介入4】
だから、昼12時間、夜11時間と
いうように考えるのですが、
これでは一日が23時間です。
|
|
23)ここから正解のラッシュ
24)原田さん、伊藤さん、坂口君、小林君、内山くん、
小坂くん。
|
そして、ついにチャイムがなります。
最後まで答えは教えません。
ここまで、向山学級の子どもたちの状況を記録しました。
何か気づきませんか?
「194人目。座間さんが正解」
のような記述。
数値が正確すぎませんか?
これは、どういうことでしょうか。
持ってきた子の人数と名前を、向山は全部覚えていたのでしょうか。
いえ、おそらくその場で記録したのでしょう。
「正の字」などを書きながら、持ってきた子たちの名前をメモしていったのではないか。
私はそう推定します。
この向山の「数値」に基づいた実践記録。
これがあるおかげで、私たちは
「自分たちの追試と比較検証」
ができるのです。
これが「現場に根ざした教育研究」の基本だと思います。
|
 |
| 6 向山の5種類目の介入 |
さて、上記の記録によれば、
子どもたちが問題に取り組んでいる間
|
|
向山は4回しか発言していない
|
ことになります。
しかし、それは正確ではありません。
もう1種類、向山は「何度か」介入しています。
それがこれです。
|
【介入5】
途中で何度か「答えを教えようか」という
|
何度言ったのかはわかりません。
授業後半に子どもたちの様子をみて言ったのでしょう。
子どもたちは
|
|
必死で「教えないで」と叫んでいた
|
ということです。
できなかった子は休み時間まで解き続けます。
まさに、究極の熱中状態ですね。
|